- HOME
- 提言・ニュース
- 政策テーマ
- 【パブコメ】厚生労働省「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案」のパブリックコメントに意見を提出しました
【パブコメ】厚生労働省「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案」のパブリックコメントに意見を提出しました
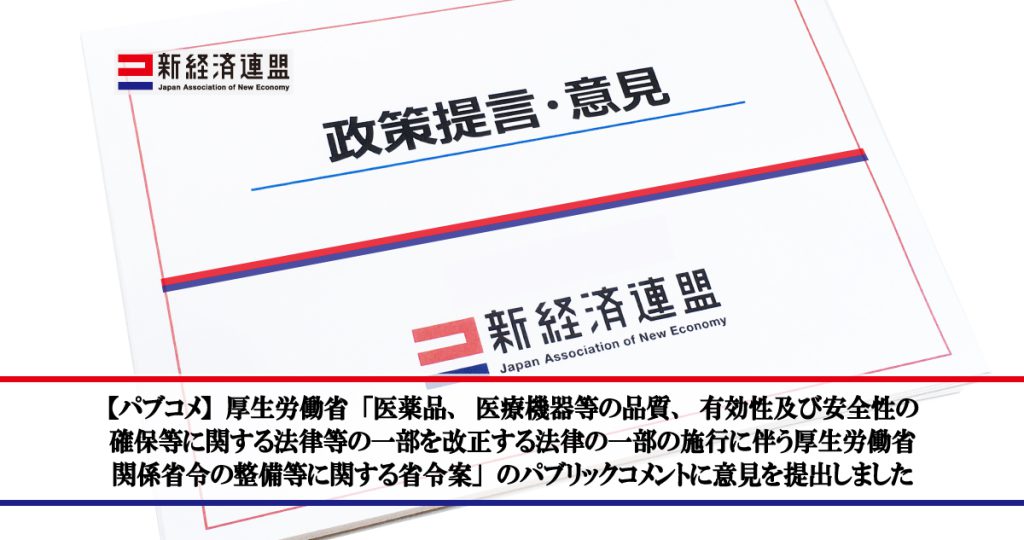
2025年11月1日、新経済連盟は、厚生労働省が実施した「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案」に対する意見を提出しました。
【提出意見の概要】
1. 全体を通した意見
• 市販薬の過剰摂取防止策は、販売時点での対応だけでなく、孤独や孤立への対策や普及啓発も含めた政府全体の取組として進めるべきであるとされているが、今般の医薬品の販売方法の規制が、市販薬の濫用防止に効果的であるのか、客観的・科学的根拠に基づき検討がなされるべき。また、医薬品の価格の推移や適正利用者による医薬品へのアクセスの観点も踏まえ、合理的かつ効果的な規制であることが確認できない場合は制度の見直しを行うべき。
2. 各項目に対する意見
• オンライン服薬指導による要指導医薬品の販売方法について、「オンライン服薬指導を行うことができるとその都度責任をもって判断するときに行われる」とされているが、対面とオンライン服薬指導それぞれの場合の責任は具体的にどのように担保されているのか明らかにされたい。対面における「責任」が不明瞭なままオンライン服薬指導にのみ殊更に資格者の責任を加重することのないよう注意されたい。
• 指定濫用防止医薬品の販売方法については、改正薬機法案に対する附帯決議において「医薬品へのアクセスを不当に制限することがないよう、多様な販売形態を考慮し、濫用防止と利便性のバランスに配慮した規制とすること」とされている。一方、濫用等の恐れのある医薬品の販売方法の変更に関してECプラットフォームの実施したアンケートによると、指定濫用防止医薬品をビデオ通話により販売する予定があると回答した事業者はごくわずかであり、販売する予定のないとした事業者の理由の多くが「システムの導入が困難」「販売フローが複雑になりすぎる」とのことである。多くの医薬品ネット販売店舗で販売が取りやめられる状況は適性使用者の医薬品へのアクセスが阻害されることとなる上、ビデオ通話に濫用防止効果があることの合理的根拠が示されていないこと、テキストベースのネット販売で濫用が促進されるような事実は示されていないことからも、ネットの特性を活かし、対面やビデオ通話によらない販売方法を「その他の」方法として省令に追加すべき。
• 指定濫用防止医薬品の情報提供の方法に関する規定のうち、購入者に対して個別に情報を提供することなどの規定については、第一類医薬品の販売規定と同様のものとなっている。第一類医薬品と指定濫用防止医薬品は、副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれの程度が異なることから、従前の規定に基づく医薬品の分類ごとの情報提供の方法を尊重した上、医薬品へのアクセス等の利便性にも配慮し、適正利用者による購入を妨げるような制度とならないよう留意すべき。
• この省令にて規定する指定濫用防止医薬品の販売又は授与時の確認事項については、ビデオ通話によらないネット販売でも確認が可能な事項であることから、ネット販売も可能となるよう、対面やビデオ通話によらない販売方法を「その他の」方法として省令に追加すべき。
• 対面販売時における指定濫用防止医薬品の陳列設備及び専門家の継続的な配置について、今般の制度改正により濫用防止に効果的であるのか、医薬品濫用者の当該医薬品の入手経路等、客観的なデータを用いて検証し、濫用防止への効果が不十分である場合、対策の見直しが検討されるべき。

