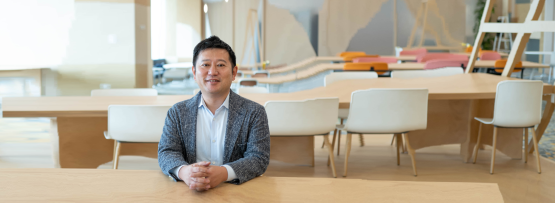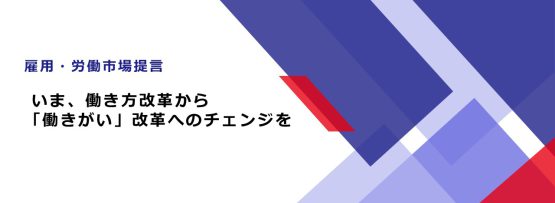新経済連盟では、事業・経営面で最先端を走るスタートアップを経営し、アントレプレナーとしての行動・挑戦が、新経済連盟の目指す JX(Japan Transformation)*と合致する経営者を表彰する、「JX Awards」を実施しています。
今年の選考委員会にて選出された「JX Awards2025」受賞者のうち、大賞を受賞されたエイターリンク株式会社の岩佐 凌 代表取締役CEOに、インタビューを行いました。
▼JX Awards2025について
https://jane.or.jp/proposal/pressrelease/25189.html


1.電力の「空間伝送」に着目
ーこの度はJX Awards2025 大賞の受賞、まことにおめでとうございます。早速お話を伺えればと思います。
御社はワイヤレス給電で大きな注目を集められていますが、なぜワイヤレス給電に着目して創業に至ったのか、経緯を教えてください。
きっかけは、米国シリコンバレーで現CTOの田邉勇二と出会ったことでした。当時、田邉はスタンフォード大学に在籍し、メディカルインプラントデバイスの研究開発をしていました。例えば心臓ペースメーカーで、田邉の技術は、従来の1/1000サイズの小型化を可能にするものでした。その鍵が、マイクロ波方式のワイヤレス給電です。この技術は、中距離に電力を空間伝送することができ、ペースメーカーのバッテリーを無くすことが可能となります。
当時私は、新卒で入社した岡谷鋼機で働いていたのですが、自動車関連のプロジェクトに携わる中で、顧客のファクトリーオートメーション(FA)工程での断線問題を目にしてきました。FA工程では、わずか1mの間に無数のセンサが配線されています。それらの配線が1本でも断線すると、工程全体がストップします。自動車の工場は1分間で数百万円もの経済価値を生むと言われており、短時間の停止であっても巨額の経済損失が発生してしまいます。ワイヤレス給電は、このFA領域のペイン解消が可能な技術だと直感し、非常に大きな可能性を感じました。
帰国後、社内の新規事業として立ち上げる道も模索しましたが叶わず、それならばと、会社を辞めて起業の準備をし、田邉を誘って立ち上げたのがエイターリンクです。

2.ワイヤレス給電を将来のインフラ技術に
ーワイヤレス給電とはどのような技術ですか。これまでどのような技術的なハードルがあり、なぜそれが可能になったのでしょうか。
当社のコア技術は、マイクロ波方式のワイヤレス給電で、技術の構想は、100年以上前から存在していました。発明家の二コラ・テスラが実用化に向け様々な実験を行いましたが、成功には至らず、その後も長く実用化はされていませんでした。100年以上もの間、実用化できなかった最大の理由は、電力の伝送距離が短かったからです。技術的な詳細は控えますが、当社は、最大17mの給電距離を実現しています。田邉が持つ無線アンテナの技術に加え、大手企業出身のエンジニアが多数在籍しており、技術的なブレイクスルーに成功しました。
ーワイヤレス給電に係る現在の業界動向はどのようになっていますか。業界内での御社のポジショニングと併せてお教えください。
当社はこの業界では後発で、先行企業は欧米含め世界中で数社が存在しています。この中で、当社の最大の強みは給電距離が長いことです。ユースケースも複数あり、一定の売上も創出できています。技術的・事業的に当社に優位性があると考えています。
ー国内で事業を展開するにあたり、日本の法規制など、ビジネス上のハードルが存在しましたか。
創業時、給電のために電波を出すことは法律で規定されておらず、違法扱いでした。総務省や関係各所へ向けた働きかけを地道に続ける中で、2022年に省令改正が行われ、電波利用が合法となりました。
ーグローバルの面でも、6Gにおける国際規格統一に向けて、WRC-23(世界無線通信会議)に日本代表団として参加されるなど、標準規格の重要性を訴える活動をされていますが、どんな背景がありますか。
実は、給電用途での電波利用が法整備されたのは日本が最初といわれています。新しい技術を社会に実装するためには、各国での法制度化はもちろん、利用する電波帯域の統一や、製品開発における様々な機器仕様や検査基準なども標準化していく必要があります。市場の参入障壁を下げ、機器開発メーカーだけでなく検査装置メーカーなど、様々なプレーヤーがワイヤレス給電技術を利用できるようにすることで、市場全体が拡大します。
ワイヤレス給電はジェネラル・パーパス・テクノロジー(汎用技術)であり、将来のインフラ技術となる可能性に満ちています。これまで実用化がされてこなかったからこそ、既存の規制が存在せず、ルールや市場をゼロから作っていくことが重要です。当社のビジネスは、既存の枠組みでシェアを伸ばすのではなく、新しい市場や枠組みをゼロから作ることを狙っています。当社がルールメイキングを重視するのはこのような背景からです。

ー御社は現在、FA・ビルマネジメント・バイオメディカルの三分野にわたり事業を展開されていますが、今後、ワイヤレス給電の応用によって影響を受ける業種・分野には、他にどのようなものがありますか。
リテールや物流にも応用できるとみています。当社が現在ビルマネジメント事業で販売している温湿度センサは、人の在不在の情報も取得することができます。店舗における人流を可視化することで、最重要課題である販売・マーケティングに活用いただくことが可能です。物流では、倉庫における荷物管理や、貨物運搬時の電子タグなど、業務効率化につながる様々な可能性を秘めています。将来的にはレンズ上に映像を投影したり、オートフォーカス機能を搭載して遠近両用を可能にしたりするスマートコンタクトレンズを実現したいと考えます。宇宙からの給電も長期的に取り組みたい課題の一つです。
ーワイヤレス給電によって、我々の生活面はどのように変化すると思いますか。
2040年には6G回線が普及し、世界中で45兆個ものセンサが駆動するIoT社会が到来すると言われています。ボールペン1本にもセンサが搭載され、書いた文字や絵が常にデジタルデータとしてバックアップされる…そんな未来が訪れるのも遠くはありません。これほど大量のセンサを全て電源コードや電池で駆動させるのは経済コストの点から不可能であり、ワイヤレス給電などの全く新しい給電方法が必要です。
今後ワイヤレス給電が普及した社会は、究極的にはバッテリー交換や配線が不要なセンサ社会をもたらします。体内、体外を問わず、地球上で膨大なセンサが駆動し、生体データや環境データがありとあらゆる場所で取得されるようになります。個人から都市・産業までのデジタルツイン環境がリアルタイムで更新され、医療・産業・都市運営における様々な意思決定を飛躍的に精緻化・効率化することが可能です。社会基盤に変革をもたらすほどのインパクトになると思います。

3.周囲からの反対で成功を確信
ー起業当時から、その後の現在に至るまでの事業展開(FA・ビルマネジメント・バイオメディカル)について、明確なイメージはありましたか。
FAやバイオメディカルについては、ワイヤレス給電のユースケースとして当時から明確なイメージを持っており、特にFAについては量産化まで辿り着きました。ビルについては、創業後に様々な事業者とディスカッションする中で事業化が進みました。こちらも量産化まで完了しており、様々な企業から発注いただいています。当初描いていた仮説は一定当たっていたと考えてます。
ーリスクのある起業という決断に踏み切れた背景として、どのような理念や信念がありましたか。ご自身の生い立ちなども踏まえて教えてください。
父が会社を経営していたこともあり、起業の抵抗感はありませんでした。ワイヤレス給電の会社を起業することについても、創業前に様々な人に意見を聞きましたが、答えはNO。全員からことごとく反対されました。しかし私は、逆に確信を持ちました。全員が賛成するような事業だったら既に陳腐化しており、起業してもうまくいかないからです。これだけ全員から否定されたことで、かえってそれが自信となりました。
ー日本に拠点を置いた理由は何ですか。また、日本を拠点とすることのメリット・デメリットをそれぞれ感じられていたら教えてください。
米国では、スタートアップ企業の事業拡大において消費者向けサービスの関心が強く、産業向けのビジネスは市場が不十分と考えました。一方、日本はロボット工学や機械工学の中心地であり、世界中で販売される産業用センサの約半分は日本で製造されています。産業用ロボットの大部分も同様です。FA向けビジネスを念頭に置いたとき、日本で創業することは自然な判断でした。
日本を拠点とすることのメリットは、上述した通り世界レベルのプレーヤーが多数存在することです。実際、FAでは空圧制御領域で世界トップレベルのシェアを有する大企業と共同開発品をローンチすることができています。デメリットは特段浮かばないですね。
ー創業から現在まで、チームマネジメントや経営面で特に苦労された時期はありますか。
初期はコロナ禍だったこともあり、苦労が続きました。投資家や企業との30分のオンライン面談を朝から夕方まで、毎日十数件セットしては進展せず、ということの繰り返しでした。モックアップを作って見せにいったりしましたが、ことごとくダメ。いよいよ諦めようかと考えていた時、たまたま取り上げていただいたテレビ番組がきっかけでFAのパートナー企業とつながることができました。エピソードは挙げればキリがないですが、この時が一番印象に残っています。
ー御社の事業を通じて、世間や人々にどのような影響を与え、どのような社会を実現していきたいとお考えですか。
地球の歴史上、富の創造が起きたときには必ずテクノロジーが存在しています。例えば農業革命は、アンモニアを製造するハーバー・ボッシュ法が確立されたことが要因ですし、エジソンが発明した白熱電球は世界から夜を無くしました。通信やインターネット技術によって、物理的な距離を問わずにコミュニケーションできるようになりました。
ワイヤレス給電が普及すれば、スマートコンタクトレンズやブレインマシンインターフェースなど、新たなデジタル革命が起きます。ワイヤレス給電は、人類のデジタル世界を一つ上のレイヤーに押し上げるポテンシャルを秘めています。エイターリンクの経営を通じて、社会や地球規模の富の創造にテクノロジーで貢献したいと思っています。

岩佐CEOをはじめとするJX Awards2025受賞者に対しては、10月21日(火)開催予定の新経済連盟の周年イベント「JX Live! 2025」の当日に表彰式を行います。(昨年の表彰式の様子はこちら)
ぜひ、ご注目ください!
▼JX Live!2025イベント特設サイト
https://nest.jane.or.jp/jxlive2025/
▼参加申し込み
https://eventregist.com/e/jxlive2025
——————————————————————————
■開催日時:10月21日(火)13:00~
■会場:六本木 グランドハイアット東京(港区六本木6-10-3)
■参加費:
【新経連一般会員】 1社1名ご招待/2名以降 11,000円(税込)/人
【非会員】 22,000円(税込)/人
【学生】無料
——————————————————————————
* JX(Japan Transformation):2022年の活動開始10周年に合わせて、新経済連盟が打ち出した新たな活動指針。未来を見極める力を持ったアントレプレナー(実業家)たちが主役となり、その力を結集して日本を変えていくことを宣言している。